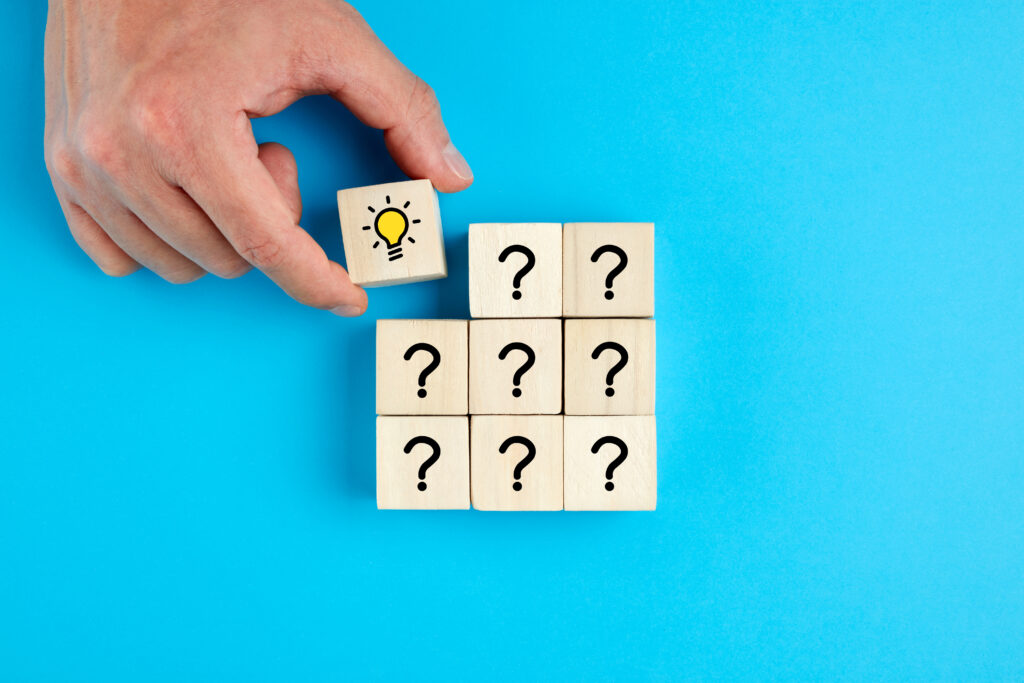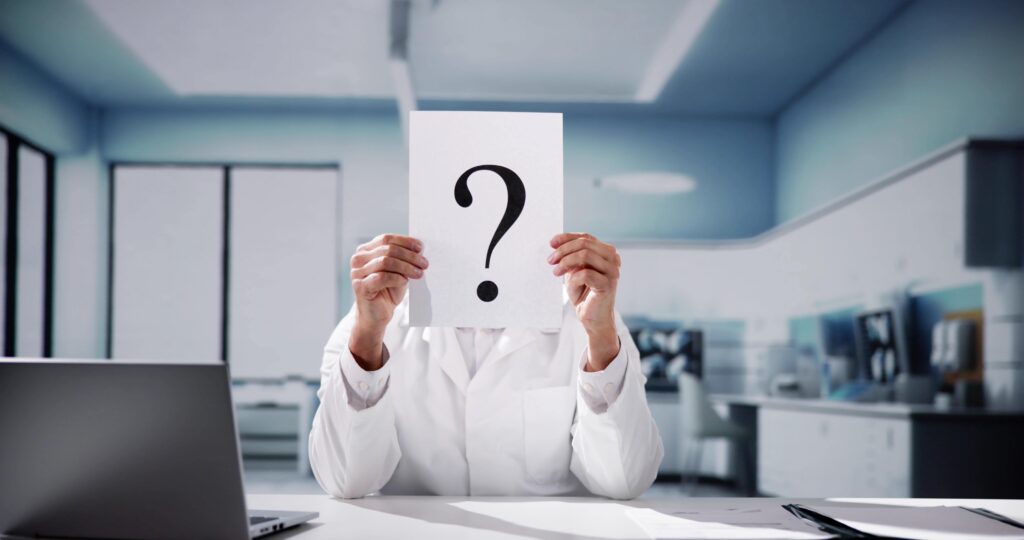
診療報酬は、医療機関の経営を支える重要な仕組みであり、私たちが安心して医療を受けるためにも欠かせません。2026年度には診療報酬改定が予定されており、制度の仕組みや支払い方式の見直しに加え、医療DXや出産費用の無償化といった政策が反映される可能性があります。本記事では、診療報酬の基本と2026年改定の予測についてわかりやすく解説していきます。
診療報酬の仕組みや支払い方式
診療報酬は、日本の医療制度を理解するうえで欠かせないキーワードです。以下では、診療報酬の基本から支払いの仕組み、そして支払い方式について解説していきます。
診療報酬の基本
診療報酬とは、病院や診療所、薬局などが提供する保険医療サービスに対して支払われるお金のことです。日本の公的医療保険制度に基づいて決められており、医療機関の主な収入源となっています。
患者さんは診察や治療を受ける際、自己負担分を窓口で支払いますが、その金額だけでは医療機関の収入は成り立ちません。残りは保険者と呼ばれる健康保険組合や国民健康保険などが負担しており、両者を合わせて診療報酬が成立します。
こうした仕組みのおかげで、患者さんは高額な医療費を直接払わずに済み、誰でも必要な医療を受けやすい環境が守られています。
診療報酬が支払われる流れ
医療機関が診療報酬を受け取るには、いくつかの手順があります。
最初に、医師や薬剤師が患者さんに行った診療や処方の内容を記録し、その内容を基に診療報酬請求書を作成します。その後、審査支払機関へ提出し、請求内容が正しいかどうかが確認されます。
審査を通過した請求書は保険者へ送付され、支払いの可否が判断される仕組みです。保険者から医療費が拠出され、審査支払機関を経由して医療機関に報酬が届く流れとなります。
この一連のプロセスによって、透明性が保たれ、不正や誤りのない形で医療機関に収入が行き渡ります。
診療報酬の支払い方式
診療報酬の支払い方式には大きく分けて2種類あります。
ひとつは「出来高払い制」です。これは、医療行為ごとに料金が設定され、実際に行った診療や検査、処方に応じて報酬が支払われる仕組みです。たとえば、血液検査をすれば検査料、点滴をすれば点滴料といったように積み重ねていきます。
もうひとつは「包括払い制」です。こちらは、ある一定の条件のもと、まとめて定額の報酬を支払う仕組みです。入院医療などで使われることが多く、医療機関にとっては効率的な運営を促す効果があります。
日本の医療制度では、基本的には出来高払い制が中心ですが、近年は包括払い制も一部取り入れるなど、バランスを取りながら運用されています。
2026年の診療報酬改定で何が変わるの?
以下では、2026年度診療報酬改定の実施スケジュールをご紹介します。診療報酬改定は医療制度に大きく影響する見直しで、医療機関や患者さんにとっても重要です。
改定のスケジュール
診療報酬改定は原則2年に1度、偶数年に行われます。これまでは4月が一般的でしたが、2024年度からは「診療報酬改定DX」という取り組みにより6月1日が実施日となりました。
そのため2026年度の診療報酬改定も、6月1日ごろに実施される見込みです。
流れとしては、2025年春から夏にかけて医療現場の実態調査が行われ、その結果を踏まえて秋に個別の検討が進められます。
翌年1月末には「短冊」と呼ばれる改定案の概要が公開され、2月には中央社会保険医療協議会(中医協)から答申が出されます。
この段階で具体的な点数が示されるため、医療機関は自院の診療や収入にどう影響するかを確認することになるわけです。
3月には疑義解釈資料が公開され、4月1日には薬価改定が実施されます。その後、6月1日に改定内容が本格的にスタートするスケジュールです。
改定を議論する場
診療報酬改定の中心的な役割を担うのは厚生労働省の諮問機関である中医協です。ここには診療側の代表として日本医師会などが参加し、支払側の代表として健康保険組合などが加わります。
診療側は現場で必要とされる医療行為を正当に評価してほしいと主張し、支払側は保険財政の安定を重視する立場を取ります。両者の意見をすり合わせながら最終的な改定内容が固まっていく仕組みです。
医療機関にとっては、中医協の議論を早い段階で把握することが欠かせません。特に2025年の後半からは改定の方向性が見えてくるため、レセプトソフトの更新や診療体制の調整など、準備を進めていく必要があります。
改定直前に慌てないためにも、情報収集を怠らないことが重要です。
2026年度診療報酬改定に向けた現在の予測
2026年度診療報酬改定に向けて、さまざまな分野で議論や準備が進められています。以下では、現時点で予測されている主な改定の焦点について整理してご紹介します。
賃上げへの対応
近年の物価上昇に合わせ、賃金の引き上げが国全体で進められています。政府は2029年度までの5年間で、実質賃金を毎年1%程度上げることを目標としています。
医療分野についても、職員の処遇改善を図るための検討が続けられているのが現状です。2024年度改定で新設された「ベースアップ評価料」は、こうした流れを受けた仕組みのひとつであり、2026年度以降も継続される可能性が高いとみられます。
さらに、介護や障害福祉分野とのバランスを取るために、医療従事者の待遇改善や業務負担の軽減策も引き続き検討されるでしょう。
医療DXの推進
国は医療DXの推進を強く打ち出しており、診療報酬改定にも反映されると予測されます。2025年12月以降はマイナ保険証が基本となる仕組みに移行するため、関連加算の見直しや廃止が検討される見込みです。
また、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの普及が遅れている現状を踏まえ、全国的な医療情報プラットフォームの整備や標準型電子カルテの本格運用が進められます。
その際には、医療DX推進体制整備加算や在宅医療DX情報活用加算の見直しも行われる可能性があります。
補助金などの支援策が設けられることも予想され、医療機関は新しい仕組みに適応する準備が必要です。
OTC類似薬の保険給付の見直し
少子高齢化が進む中で、社会保障制度の持続可能性が大きな課題となっています。
その一環として、OTC薬(市販薬)と処方薬で効能が重なるものについては、できるだけ市販薬で対応する方向に見直され始めているのが現状です。これにより医療費の削減を図り、現役世代の負担を軽減する狙いがあります。
地域ごとに薬の使い方を最適化する「地域フォーミュラリ」の全国展開も視野に入っており、診療報酬改定を通じて新しい仕組みが導入される可能性があります。
出産費用の無償化
政府は2026年度を目標に、標準的な出産費用を無償化する方針を示しています。
妊婦健診への公費負担を拡大するほか、出産に関する情報を提供する「出産なび」の機能強化、そして小児周産期医療体制の整備も進められる予定です。
安全で質の高い無痛分娩を選べる体制の構築も課題とされています。こうした取り組みを診療報酬に反映させるために、点数の見直しや新しい評価項目の設定が行われる可能性があります。
リフィル処方箋の普及
リフィル処方箋は、同じ薬を繰り返し処方できる仕組みで、患者さんの受診回数を減らし、医療機関の負担を軽くする効果が期待されています。
政府は重複処方や無駄な検査を抑える手段として普及を後押ししており、診療報酬改定で新たな評価や加算が検討される可能性があります。
長期処方を安全に行うためのルール整備と併せて、保険外併用療養費制度の対象拡大なども進められると考えられます。
まとめ
診療報酬は、医療機関が安定して診療を行い、患者さんが安心して医療を受けられるための大切な仕組みです。支払い方式や流れを知ることで、制度の背景が理解しやすくなります。さらに2026年の改定では、賃上げへの対応や医療DXの推進、出産費用の無償化、OTC薬の活用促進などが議論されており、医療現場にも生活者にも大きな影響を与えると予想されます。改定の方向性を知っておくことは、医療のこれからを考える上で役立つでしょう。
 引用元:https://mmso.jp/jim全員が事務長経験者かつ経営者のプロ集団!負担軽減からクリニックの発展まで支援する”稼げる”事務長代行
引用元:https://mmso.jp/jim全員が事務長経験者かつ経営者のプロ集団!負担軽減からクリニックの発展まで支援する”稼げる”事務長代行- Point
スタッフ全員が事務長経験者かつ会社経営をしているプロ集団
- Point
診療報酬の活用や医療機関との連携強化など、増収対策も実施
- Point
分院や事業承継、介護事業参入など、事業拡大の全ての対応実績とノウハウあり
- Point
株式会社医療経営支援事務所
おすすめのクリニック事務長代行サービス比較表
| イメージ |  引用元:https://mmso.jp/ |  引用元:https://clinic-manager.net/ |  引用元:https://jimu-choo.jp/ |
| 会社名 | 株式会社医療経営支援事務所 | MOCAL株式会社(クリニックマネジャー) | 株式会社ジムチョー |
| 代行業務 | ・業者との価格交渉(コスト分析も含む) ・SEO対策、MEO対策で集患強化(アクセス分析も含む) ・採用業務対応(求人作成、面接調整・同席など) ・病院、クリニックへの訪問(集患目的) ・厚生局への届出対応(資料作成、提出など) ・業務改善PDCA推進(残業対策、待ち時間対策など) ・診療報酬の算定強化(増収目的) ・診療報酬の改定対応 ・スタッフの相談対応 ・経営分析、課題解決に向けたPDCA推進 ・税理士からの会計報告対応、財務改善に向けた協議、銀行対応 ・既存の事務長の育成 | ・総務・秘書 ・院外マーケティング ・渉外業務 ・人事業務 ・マネージャー業務 ・参謀・ブレーン | 診療業務以外の業務全て |
| 料金プラン(例) | ▼クリニックのみの対応の場合 ・月2日訪問+リモート対応(事務長代行):33万円 ・リモート対応のみ(事務長代行):22万円 ▼クリニック+介護事業所の対応の場合 ・月2日訪問+リモート対応(事務長代行):38.5万円 ・リモート対応のみ(事務長代行):27.5万円 ※料金は希望の訪問日数により変わります。 ※月1日からも対応可能です。 | ・経営参謀型:22万円~33万円 ・プロジェクトマネジメント型:16万5,000円~22万円 ・総務・秘書型:22万円~79万2,000円 | ・ジムチョー®代行:応相談 ・リモートジムキョク™:9万円 ・WEBコンサル:5,000円 |
| 契約期間 | 月1回~ | 月1回~ | 記載なし |
| 事務長業務の実務支援 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 病院・クリニックへの訪問(連携強化) | 〇 | × | 記載なし |
| クリニック+介護事務所への対応 | 〇 | × | 記載なし |
| スタッフ全員が事務長経験あり | 〇 | × | 記載なし |
| スタッフ全員が経営者(経営者視点) | 〇 | × | 記載なし |
| 詳細リンク | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら |
| 公式サイト | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら |